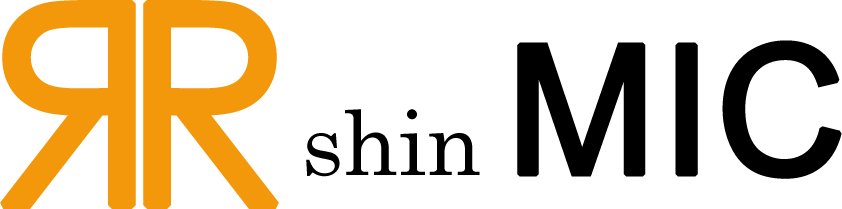探求心をアップする雑学講座
大河ドラマ「どうする家康」33話では、家康の懐刀であった石川数正が秀吉の元へ出奔してしまいました。出奔の理由についてはさまざまな説がありますが、いずれにしても徳川側の軍事機密が豊臣側に筒抜けになってしまったわけで、三河以来の軍制を武田流に改めたことからも、いかに痛手だったかが分かります。「どうする家康」の中でも家康が井伊に武田流に改めろと指示する場面があったような気がします。
そして、松本市のシンボルである松本城はその石川数正が築城したお城です。国宝松本城は地元民にとって、それなりに誇りですが、実はお城としては、かなり、しょぼかったりします。この辺りは築城時の事情を調べて見ると面白いかもしれません。

石川数正で、私がパッと頭に浮かんでくるのが「三九郎」です。
三九郎という言葉を松本市民は当たり前に使っていますが、どんど焼きのことを三九郎と呼ぶのは旧松本藩の地域限定です。どんど焼きのことをなぜ三九郎と呼ぶようになったかは、いくつか説がありますが、個人的に最もしっくりくるのが、石川数正の息子の石川康長の幼名が、「三九郎」であったいうものです。
幕府の金庫番として天下の総代官として権勢をふるった大久保長安という人物がいたんですが、死後、その不正蓄財が発覚します。これに怒った家康は、長安の息子7人と腹心だった人物を処刑します。大久保長安事件と言われるものです。そして処刑された息子の一人が石川康長の娘と結婚していました。これにより康長も処罰されることになり、松本のお殿様を辞めさせられ、豊後国佐伯(大分県)に配流となりました。
この時の康長の無念の思いがたたりにならないように、その魂を鎮めるために、どんど焼きのことを三九郎と呼ぶようになったのではないかという説です。
日常の小さな?、ふだん何気なく見ているもの、当たり前に使っている言葉、こういったものを少し好奇心を持って深堀すると、思いもよらない世界が開けて楽しいものです。
shin MICの雑学講座では、日常の小さな疑問や、ふだん当たり前に見たり聞いたりしているもの、そんなものを深堀するなかで、探求する力や視点、思考といった全てのベースになってくる力を養っていきます。
ご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。
1回1時間:4,400円(税込)

お気軽にお問い合わせください!(^^)
当たり前を深堀すれば新たな世界が開けます!
投稿者プロフィール
最新の投稿
 安曇野観光案内2025年11月9日紅葉の安曇野を愛知県からのお客様と散策
安曇野観光案内2025年11月9日紅葉の安曇野を愛知県からのお客様と散策 安曇野観光案内2025年9月25日デンマークからのお客様は山に感動!
安曇野観光案内2025年9月25日デンマークからのお客様は山に感動! 安曇野観光案内2025年9月25日綺麗な安曇野の水に感動していただきました!
安曇野観光案内2025年9月25日綺麗な安曇野の水に感動していただきました! Web3・トレーディング講座2025年5月22日Bitcoinピザデーと史上最高値更新
Web3・トレーディング講座2025年5月22日Bitcoinピザデーと史上最高値更新