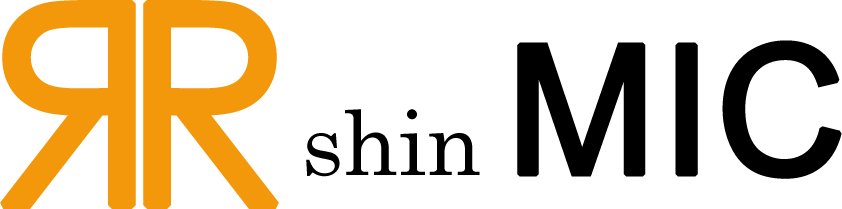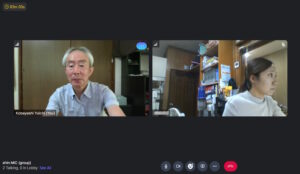ブログ
蝉の声でシシトウの話【ラジオ】
蝉の声から、なぜかシシトウの話になりました。いつもながらの雑談です。よろしければお聞きください。 shin MIC ラジオ (すごいポッドキャスト) · shin MIC ラジオ #5 蝉の声でシシトウの話
ロリポップを装ったとても不可解な詐欺メール
毎日、銀行、クレジットカード、電力会社、Amazon、宅配、レンタルサーバー、仮想通貨ウォレット、えきねっと、アダルトサイト、PCセキュリティ等々、よくも、まあ、というくらい様々な詐欺メールがやって来ます。大抵は開くこと […]
ヨーグルト家で作れるよ【ラジオ】
最近、当方イタリア人講師がヨーグルト作りにはまっているということで、ヨーグルト作りについて話してみました。相変わらずの雑談で、深い内容はありませんが、よろしければお聞きください。(^^; shin MIC ラジオ (すご […]
発音する時の舌の動きを医療用エコーを使って確認する実験
イタリア語講座に通われているお医者様から、ネイティブが発音する時の舌の動きと、我々日本人が発音する時の舌の動きをエコーを使って比較すれば、より良い発音をするための参考になるのではないかと、ご提案をいただきました。 エコー […]
止まらない円安と世界経済崩壊の足音
皆さんご存知の通り円安傾向が止まりません。1ドル160円なんて、10年前を考えればとんでもないレートです。ということで今回は珍しく外国為替について記事を書いてみたいと思います。 為替レートは外国為替市場での売買によって決 […]
Bitcoinの歴史は繰り返す!?
71000ドル台からズルズルと下落してきたビットコインですが、昨日の日足で、遂に日足一目均衡表の三役逆転となりました。つまり、さらなる続落が想定されます。 上のチャートは日足チャートですが、見事に上値を抑えられています。 […]
Bitcoinは4万ドル前後まで暴落する?
先週のトレーディング講座では、ビットコインが4万ドル前後まで暴落する可能性についてお話させていただきました。そして今週に入り、日足の上昇トレンドラインを割り込んできています。下のチャートは4時間足ですが、現在、明らかな下 […]
CSSのclamp関数が便利!
文字サイズや余白など、ディスプレイサイズのブレイクポイントごとにCSSで指定する必要があり、結構めんどくさいです。その為、これまではshin MICのサイトも、まっ、読めるし、いっか!ってな調子で、ディスプレイごとの文字 […]
ジョジョの奇妙な冒険からManic Mondayへ
昔、漫画を読んだだけでアニメは見ていなかった「ジョジョの奇妙な冒険」を、ふと思い立って、一番最初から少しずつ見始めました。「ジョジョの奇妙な冒険」のアニメを見てきている人にとっては今さらって話ですが、「ジョジョの奇妙な冒 […]
大町・松川村方面をご案内 - 安曇野案内
本日のお客様は東京の方で、前回は冬にご案内させていただいたお客様です。安曇野にも複数回来られているお客様なので、今回はメインを大町・松川村方面に絞ってご案内させていただきました。 たまたまお一人が、土木関係のお仕事という […]
HP納品後の講習を大切にしています!
shin MICではHP納品後の講習をとても大切にしています。HP納品後の更新に関しては出来る限りお客様の方で行って欲しいと考えているからです。もちろん、大きな更新や、どうしても自力で出来ないお客様に関しては更新作業を承 […]
初めてのWordPress - オンライン講座
初めてWordPressを使用してWebサイトやブログを作成してみようという方向けの講座をオンラインで提供します。ドメイン取得やレンタルサーバーの契約からスタートしますので、全く初めての方でも受講可能な内容になっています […]
#6 上田市でセミナーに出ました
長野日伊協会と協力しセミナーでお話をさせていただきました。コンテンツは:1)Bresciaの話2)イタリアの教育システムの話でした。 上田市はやっぱり綺麗な街ですね。昭和レトロでトレンドになっているだけはあります! ちな […]